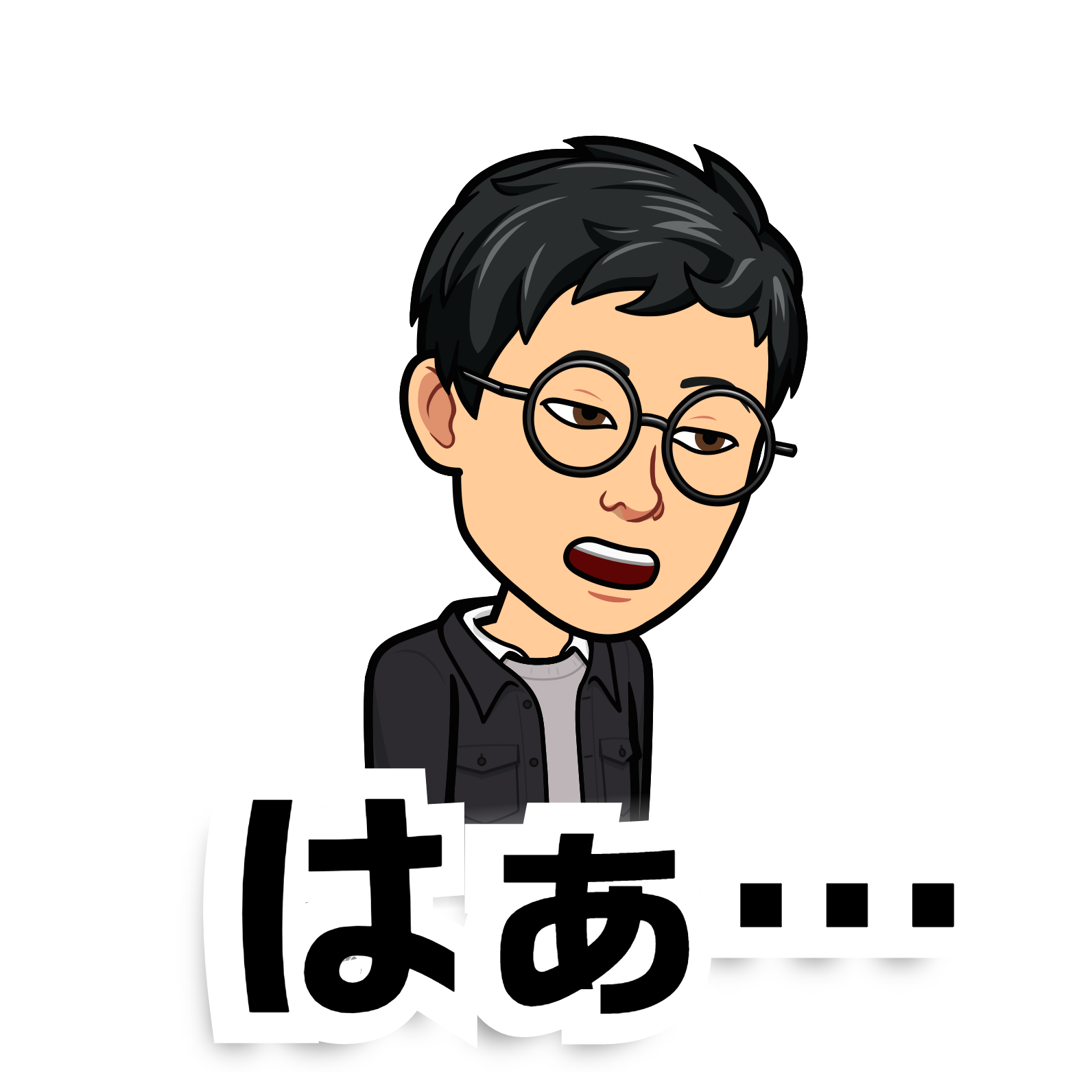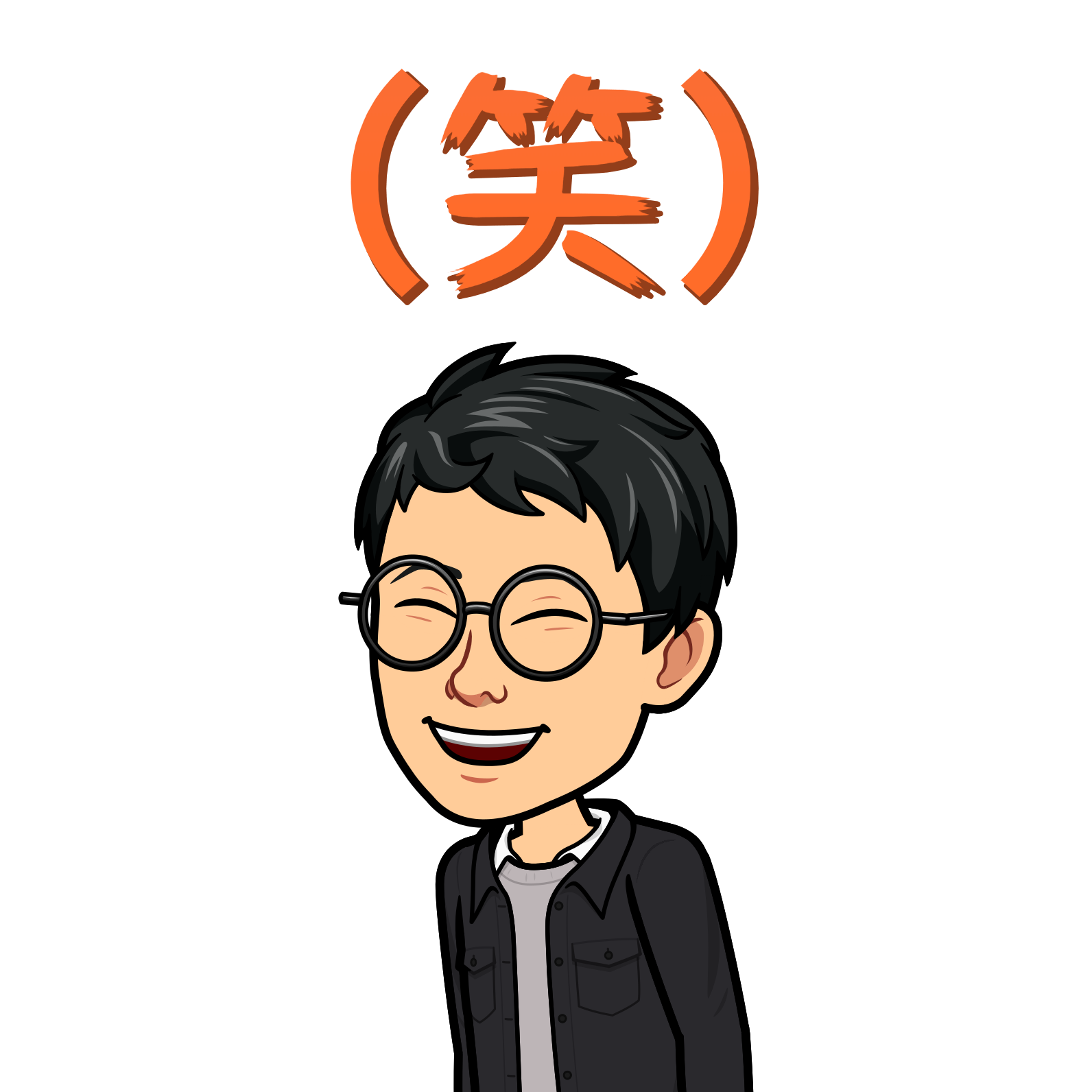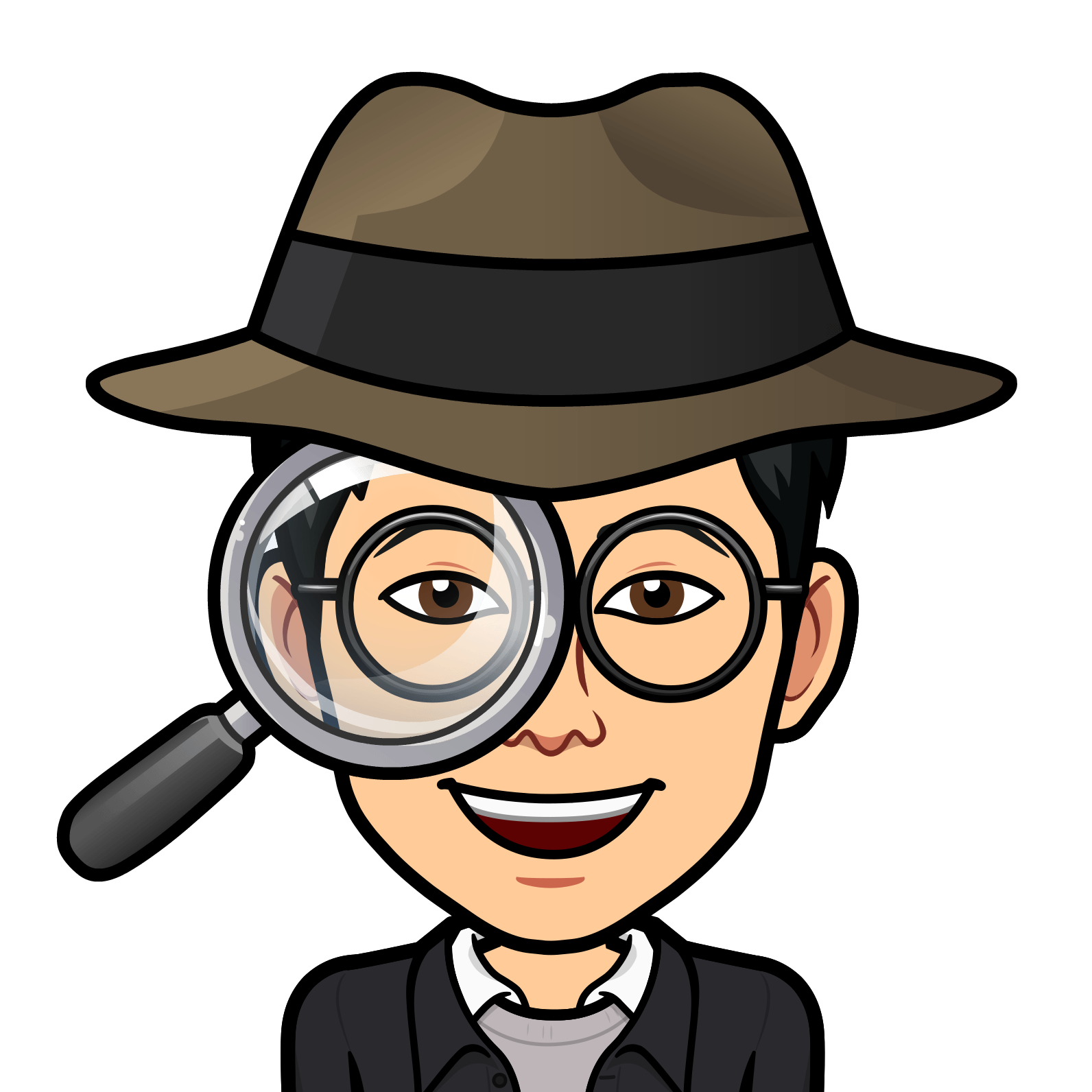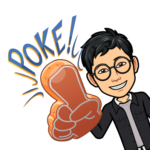こんにちは!
RISO 店長ハチです。
2024年も残りわずか。
賃貸業界では保証会社の利用が当たり前となりつつある中、入居審査の現場では新たな課題が次々と登場しています。
本日は、「入居審査」をRISO 店長ハチの視点からお届けします。
今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。
- 保証会社の役割と限界
- 入居審査の進化
- AI活用の可能性
- 入居審査のバランスの難しさ
1. 保証会社の役割と限界
保証会社活用:丸投げでは船は沈む
かつての賃貸管理は「入居審査」と「滞納督促」に精魂を注ぐ時代でした。
ベテラン管理者の
なんて武勇伝(ホントか?)を聞くと、現代の便利さに感謝せざるを得ません。
しかし、2024年現在でも保証会社が万能かというと、そうはいきません。
保証会社は「家賃滞納」をカバーしてくれますが、「夜中の騒音」や「玄関前のダンボールタワー」までは対応してくれません。
ここは相変わらず私たち管理会社が汗を流す場面です。
2. 入居審査の進化
教訓を活かした入居審査の進化
数年前、築20年のアパートで「保証会社OK」の男性を受け入れたら、トラブル続きで頭を抱えた経験がありました。
滞納はまだ保証会社がなんとかしてくれるとしても、夜中の騒音やゴミ問題、居留守などは完全に手に負えず、
…と感じたほどです。
この事件を機に、保証会社の審査結果に依存せず、「当社基準」との二重チェックを導入しました。
今では、「保証会社がNO」の場合でも信頼できる連帯保証人がいれば入居を許可するケースがあります。
一方で、「保証会社がOK」で当社がNOの場合は、迷いに迷った挙句、大家さんの利益を守るため断る勇気を持つようにしています。
3. AI活用の可能性
AIと人間のハイブリッド審査
2024年にはAI技術も進化し、入居者の「迷惑度予測スコア」を活用する時代に突入しました。
- 「この入居者、夜中のカラオケ率80%」
- 「ゴミ出しルール違反予測70%」
なんてデータが出てくると、
…と笑いつつも、案外役立つのです。
ただし、最終的な判断はやはり人間。
どんなにAIが進化しても、実際に接客して
と感じるのは私たち管理者です。
4. 入居審査のバランスの難しさ
今後の管理会社の新しい役割
これからの時代、保証会社の利用がさらに一般化し、滞納リスクの管理はますますシステム化されるでしょう。
しかし、その一方で「人間関係の管理」が管理会社の新たなミッションとして注目されるはずです。
住人同士のトラブルを未然に防ぐ仕組みや、快適な住環境を提供するための工夫が求められるでしょう。
そして、何よりも重要なのは、入居者とオーナー、保証会社の三者の間に立ち、笑顔で信頼関係を築くこと。
ここでサラリーマンの力が役立つかもしれません!
(「この部屋、家賃だけじゃなく大人の対応も保証します!」なんてどうでしょう?)
賃貸管理はバランスの仕事です。
疑わしきは断るのも一つの手ですが、物件の稼働率を上げる努力もまた大切。
「家賃保証会社」というパートナーを活用しつつ、笑顔と柔軟性を忘れずに。
2025年、さらなる進化を目指して、私たちの挑戦は続きます!
保証会社の利用が一般化する中で、賃貸管理の現場では、生活トラブルへの対応や入居審査の基準づくりがこれまで以上に重要になっています。
AI技術の進化やハイブリッドな審査方法の導入によって効率化が進む一方、管理会社の柔軟な対応と人間的な判断力が不可欠です。
空室対策と入居者トラブルのバランスをとりながら、オーナーの利益を守りつつ住人の快適な生活をサポートすることが、これからの賃貸管理者に求められる役割です。
テクノロジーに頼るだけでなく、人の温かさを活かすことが、賃貸管理の未来を創る鍵です。