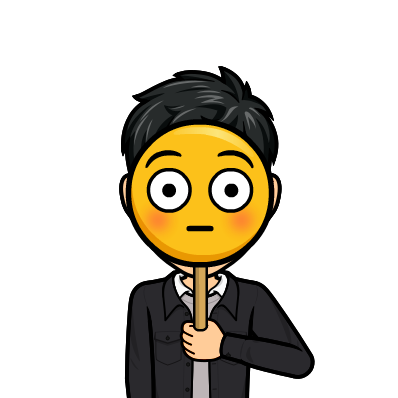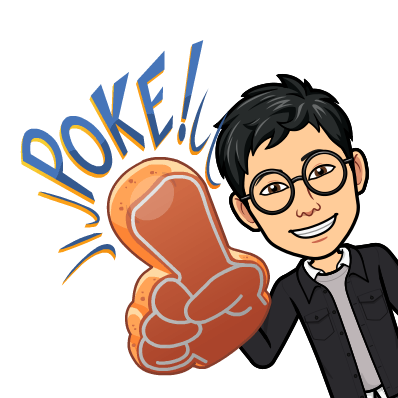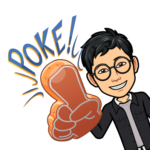こんにちは!
不動産賃貸経営のプロでありながら、サラリーマンも片足を突っ込んでいるRISO店長ハチです。
2023年のトラブルまみれの「マイナンバーと健康保険証の一体化」騒動から早1年、デジタル化の波はもはや加速の一途をたどり、不動産界にもその影響がじわじわ浸透してきています。
その象徴ともいえるのが「不動産ID」です。
今回は、この話題をもとに解説していきます。
今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。
- 不動産IDの概要
- 導入の背景と目的
- 現時点の課題
- 未来の展望とデジタル化の影響
1. 不動産IDの概要
不動産IDって何?17桁の「おうちのマイナンバー」
「不動産ID」とは、土地や建物を特定するための17桁の番号のことです。
既に存在する13桁の「不動産番号」に、部屋番号などの「特定コード」を追加して構成されます。
例えば、201号室なら「0201」を加えて17桁に。
これで、建物も部屋もピシッと識別!
まさに「おうちのマイナンバー」です。
ただ、個人的にはこの17桁を覚えるのは無理ゲーだと思っています。
せめて語呂合わせでも考えられる仕様にしてほしいものです。
「2103 6210 117 714 007」
「フドウサン ロフト イーナ ナイス オーナー」
なんて感じで!
2. 導入の背景と目的
不動産ID導入の背景には、不動産情報のバラバラ管理問題があります。
2023年時点では、「地番」「住居表示」の違いで迷子になる土地情報、下水道は市役所、ガスは民間会社…と、手続きが煩雑そのもの。
しかし、不動産IDで一元化が進むと、次のようなメリットが期待されています。
オーナーや消費者のメリット
- 情報収集がスムーズに!
オーナーが物件の修繕履歴やローン履歴を簡単に確認可能!
消費者も物件の詳細を素早く把握できるため、
消費者写真と違うじゃん!…というガッカリ体験が減少。
- 手続きの簡略化
売買や賃貸契約、相続手続きまで、IDひとつでパパっと完了!
家主印鑑証明どこ行った?…と探し回る必要がなくなりそうです。
- フェイク物件撲滅!
部屋探しサイトの「架空物件」や「重複掲載」問題が解消され、利用者の満足度がアップ!
これで「おとり広告」に泣かされることも激減するでしょう。
ちなみに、オーナーとしては、不動産ポータルサイトでの重複掲載がなくなれば、競合との比較が透明化されるため、価格設定もより適正化されるはず。
「高くても価値がある物件」と認められるようになれば、大家の私たちにも大きなメリットです!
3. 現時点の課題
現時点では、不動産IDの導入に向けた準備は進んでいるものの、実現にはまだ時間がかかりそうです。
特に問題となるのが以下の点
- 各機関の情報をどうやって統一するのか?
- デジタル化のコストを誰が負担するのか?
- プライバシー保護の観点からの懸念
2024年も、不動産ID導入の議論は進む一方で、各プレイヤー間の調整が難航中。
特に、不動産業者間の足並みの乱れは課題です。
…と言いつつ、
…と押し付け合いしている光景が目に浮かびます。
4.未来の展望とデジタル化の影響
不動産経営者からひと言:未来の大家業はこう変わる!?
不動産IDが完全に導入された未来では、オーナー業もますます効率化されるでしょう。
物件の管理がワンクリックでできるようになり、空室対策や修繕計画もスマート化。
「忙しいオーナー」をネタにするのも時代遅れになるかもしれません。
ただ、「効率化」と聞くと、私みたいな人間はは少し寂しい気も…。
手続きミスで大慌てするエピソードも消えたら、、、
…とはいえ、未来の便利さには抗えません。
不動産業界のデジタル化が進む2025年以降、オーナーとしても、時代の流れに乗って「デジタル化対応型大家」を目指していきましょう。
未来はきっと明るい…
そして必ずオチがある。
その繰り返し。
不動産IDとは、土地や建物ごとに割り振られる17桁の「不動産のマイナンバー」のような存在であり、分散している不動産情報を一元化することで、オーナーや消費者に利便性をもたらす取り組みです。
不動産情報の管理や手続きが効率化されるだけでなく、適正価格での取引や架空物件の撲滅といった信頼性向上も期待されています。
ただし、現時点ではプライバシー保護や導入コストなどの課題が残されており、まだ完全実現には時間が必要です。
しかし、不動産業界全体のデジタル化が進むことで、無駄な手間が削減され、よりスマートな未来が訪れる可能性があります。
不動産IDは、業界の効率化を進める「未来の鍵」。
これからの変化を前向きに楽しみつつ、時には冗談を交えて、不動産の新時代を迎えましょう!