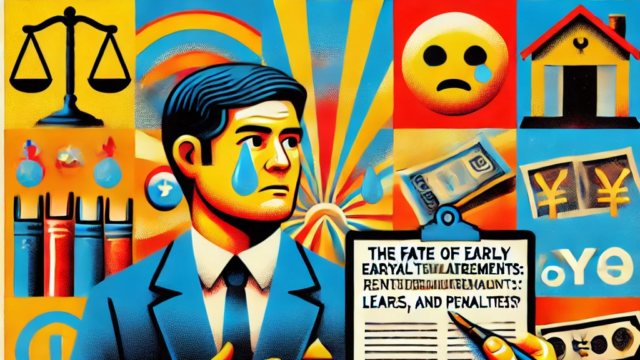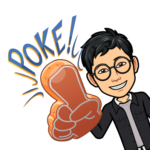こんにちは!
RISO 店長ハチです。
賃貸借契約における「修繕義務」と「立ち入り拒否権」をめぐる問題は、引き続き大家さんと入居者の間で火花を散らすテーマとなっています。
今年も全国で「立ち入り拒否」のドタバタ劇が展開され、「貸主 vs 借主」という関係がまるでバラエティ番組のように世間の注目を集めました。
さて、本題に入る前に、今回のポイントはコチラ!
今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。
- 法律の基本的な理解
- 具体的な判例の学び
- 賃貸経営の実務的視点
- 今後の課題と対策
1. 法律の基本的な理解
まず法律的な基本を復習しておきましょう。
民法606条の定める修繕義務と立ち入り拒否権の関係について、以下の条文が基盤となります。
【民法606条】
- 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 - 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
これにより、大家さんが修繕を行うためには入居者の居室に立ち入らざるを得ない状況が多いわけですが、問題はここからです。
「立ち入り」一つで信頼関係が崩れるかどうかという点が、現場での最大の課題となっています。
2. 具体的な判例の学び
【ケーススタディ:漏水調査拒否事例の再考】
2024年も引き続き注目されたのが、過去の「漏水箇所の調査立ち入り拒否」に関する東京地裁の判例(平成26年10月20日)です。
この事例では、上階の賃借人が漏水調査を拒否し続けたため、賃貸人が契約解除を主張し、裁判所が「信頼関係の破壊」を理由に解除を認めたものでした。
裁判所は「正当な理由なく立ち入りを拒否する行為は、契約上の債務不履行である」と認定しました。
さらに、拒否を続ける借主が条件として漏水と無関係な要求をしていた点も「信頼関係破壊」と判断されました。
3. 賃貸経営の実務的視点
さて、この問題、真面目に考えると堅苦しいですが、賃貸経営者としては「笑いのネタ」も必要です。
最近ではこんなブラックユーモアも流行しています。
入居者さん、それでも調査拒否ですか?
入居者との信頼関係を築くには「交渉スキル」と「適切な説明」が鍵です。
裁判沙汰に持ち込む前に、穏便に解決できる手段を模索しましょう。
4. 今後の課題と対策
これからの賃貸経営では、修繕や立ち入りに関するトラブルを減らすための 「契約書の明確化」 が重要になるでしょう。
AIを活用して入居者の疑問や不安に事前対応する仕組みも普及しつつあります。
また、修繕作業時の「立ち入りカメラシステム」の導入や、非対面でのトラブル解決方法が一般化する可能性もあります。
大家業には笑いと涙が絶えません。
しかし、法律や技術を味方につけて、借主と円満な関係を築くことがトラブル回避の第一歩です。
賃貸経営における法律知識と実務的な課題を理解することは、トラブル回避の第一歩です。
信頼関係を築き、未来の展望を見据えた対応を心がけることで、双方が安心して暮らせる環境を作ることができます。
ユーモアを交えながら学び、前向きな姿勢で賃貸経営を楽しみましょう!