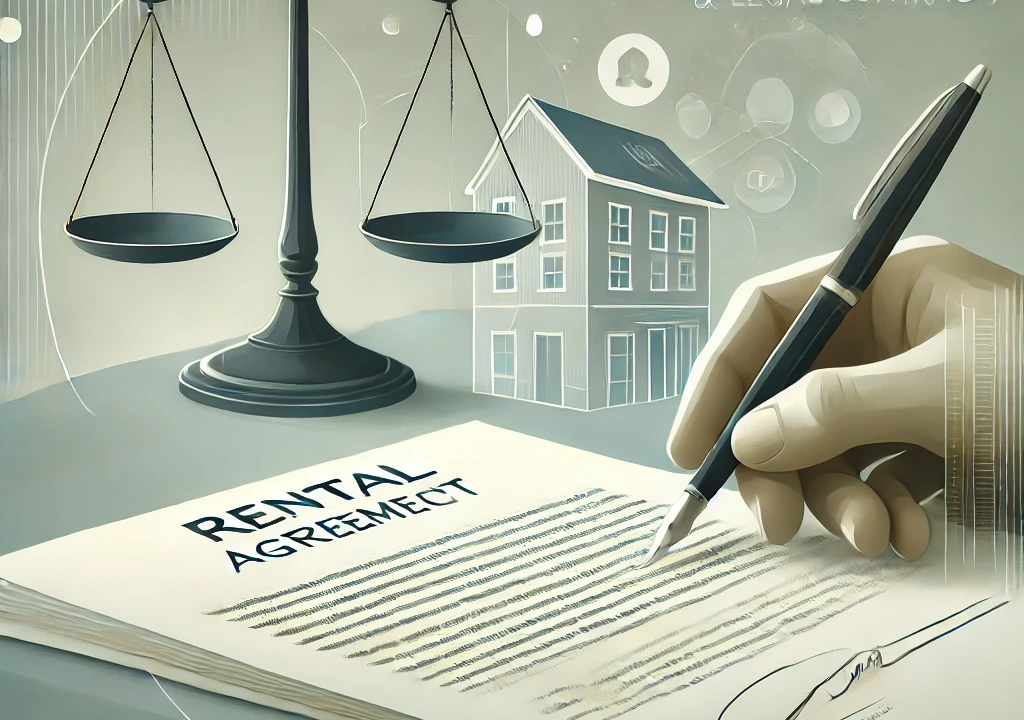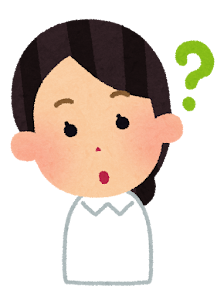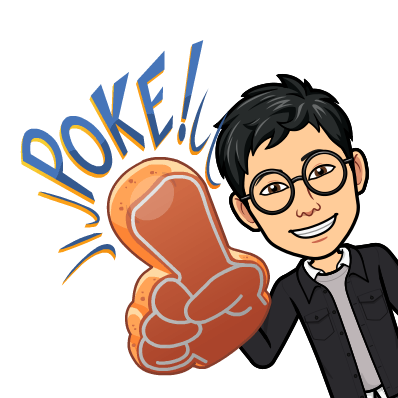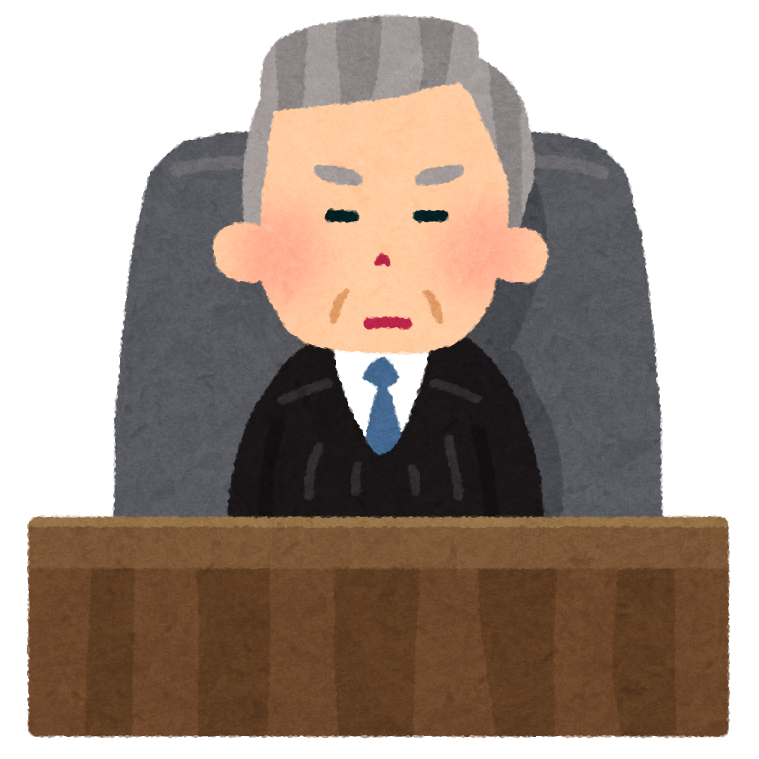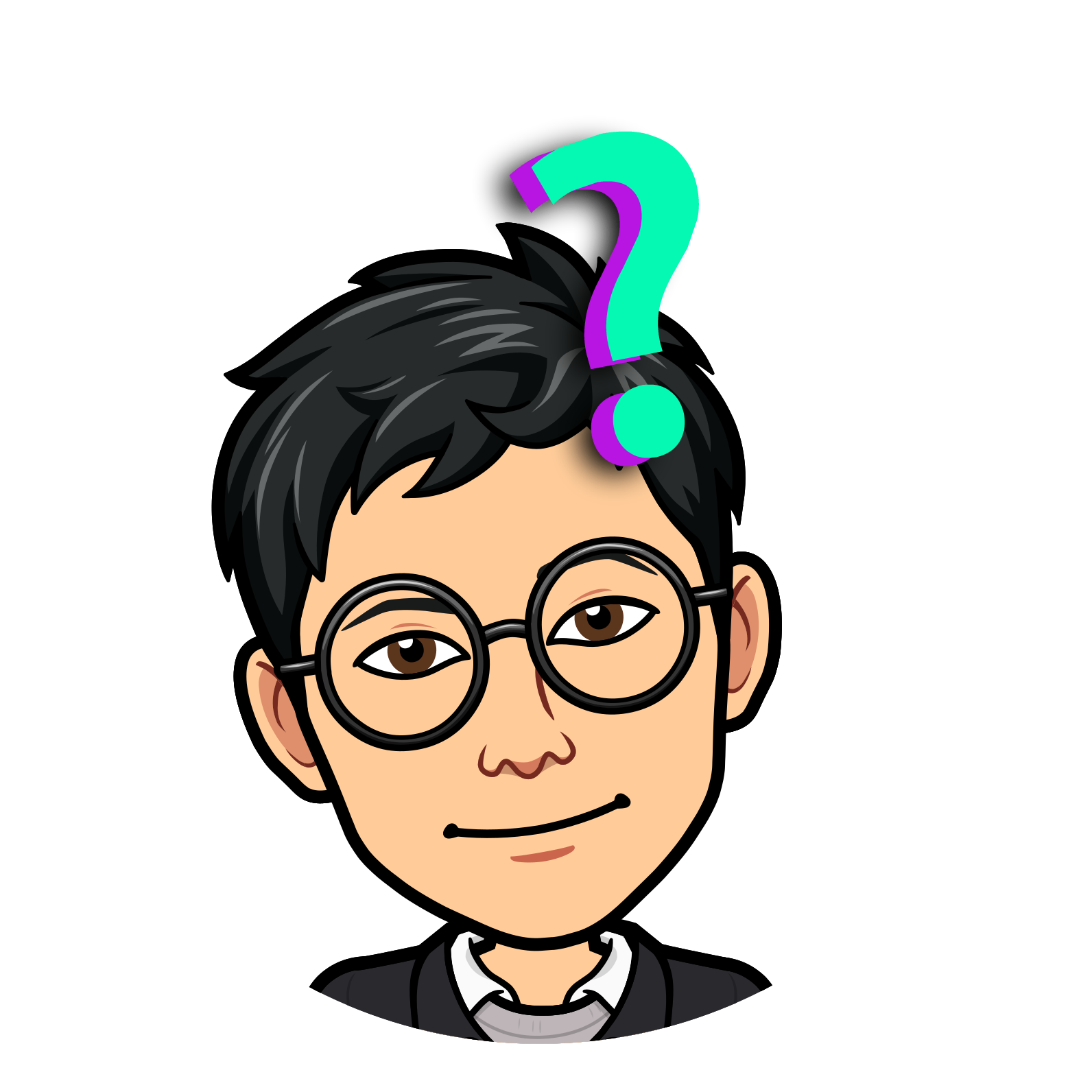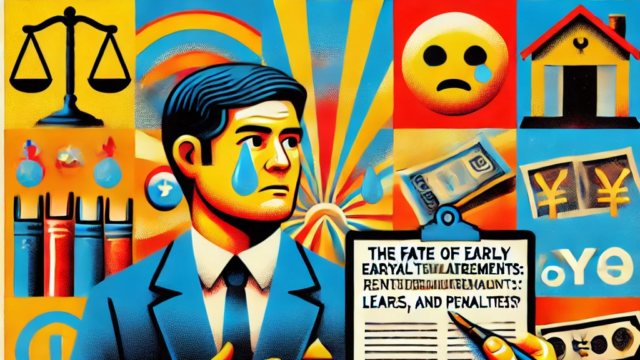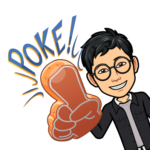こんにちは!
RISO 店長ハチです。
今回は「改正民法の保証契約規定」についてご紹介いたします。
今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。
- 改正民法による保証契約のルール
- 賃貸借契約の更新時の保証人の責任
- 更新の形式による扱いの違い
- 注意点と実務的対応
- 今後の展望
1. 改正民法による保証契約のルール
保証人さん、逃げられない運命の更新劇
改正民法の施行以降に賃貸借契約が更新された場合、従前の連帯保証契約には改正規定が適用されるのか?
2020年4月1日に改正民法が施行されてから4年半。
法律が変わった当初は
…と頭を抱えた大家さんや不動産業者も、今では慣れたもの。
ですが、この改正民法465条2第2項、保証人の責任を明確化するために極度額を定めなければならないというルール、実はまだ混乱がくすぶっているんです。
特に
…という疑問。
まるで家の壁に染み込んだ煙のように消えません。
更新のたびに保証人との合意は必要か?
これ、答えはズバリ
なんです。
なぜなら、最高裁の判例(平成9年11月13日)によれば…
- 基本的には更新しても保証人の責任はそのまま継続する。
- 但し、
…というような場合は、例外的に責任が継続しない。裁判官いや、これはもう保証人さんに責任を押し付けるのは信義則に反する!
保証人さん、安心してください。
よほどの特段の事情がない限り、あなたの責任はずっと継続します(嬉しい?悲しい?)。
2. 賃貸借契約の更新時の保証人の責任
極度額が定められていない場合は?
保証契約が改正民法施行前のものだった場合、更新後も極度額の記載がなければ
…と思う方もいるでしょう。
しかし、法務省や東京地裁の判例(令和3年4月23日)によれば、更新時に「新たな保証契約の締結がない場合」、従前の契約の効力はそのまま維持されるという解釈が一般的です。
これってつまり、保証人は「自動延長チケット」を勝手に渡されている状態。
いつの間にか、次のステージへ連れて行かれるんです。
もし
…と思ったとしても、契約の仕様上、そこから逃げるのは簡単じゃありません。
3. 更新の形式による扱いの違い
保証契約を更新する場合は要注意!
もし大家さんや賃借人が、
…と張り切って保証契約を更新するとします。
その場合…
改正民法が適用されますので、極度額を定めておかないと保証契約は無効になってしまいます。
この点だけは注意が必要です!
賃借人との更新合意書をサインするついでに、保証人さんからもサインをもらおうとするなら、極度額を忘れずに設定してください。
これを怠ると、
…と言われかねません。
4. 注意点と実務的対応
法定更新の場合はどうなるのか?
もし契約が「法定更新」される場合(更新の合意もなく、自動更新条項もない場合)、これも先ほどの東京地裁判決を参考にすると、保証人の責任は従前と同様に継続するというのが基本的な考え方です。
ただ、保証人としては
せめてお知らせくらい送ってよ!
…と文句の一つも言いたくなるところ。
実務では保証人に対して何らかの通知をするのが親切ですが、これを怠ると
とモメる可能性もあります。
5. 今後の展望
さて、2024年も終わりが見えてきた今、賃貸市場は法改正や規制強化が次々にやってきています。
保証人制度についても議論が続いており、近い将来、さらに透明性や公平性を求めるルールが追加されるかもしれません。
この際、保証人を巻き込む更新手続きをシステム化し、
…なんて導入するのも一案。
デジタル時代、保証人の負担も軽減される仕組みが求められるかもしれません。
2020年4月1日に施行された改正民法により、保証契約には「極度額」を明記することが必須となり、未記載の場合は無効になるという重要なルールが導入されました。
一方で、賃貸借契約が更新される際には原則として保証人の責任は継続しますが、新たに保証契約を結ぶ場合には極度額の設定が求められます。
更新の形式(自動更新・合意更新・法定更新)によって若干の解釈の違いがあるため、実務においては適切な対応が必要です。
さらに、保証契約や更新手続きのデジタル化が進む中、賃貸人は保証人への通知や極度額の設定を怠らないことが求められます。
法改正や規制強化の動向にも注意を払う必要があるでしょう。
保証契約は法律の舞台で永遠にスポットライトを浴び続ける主役です。
法律と仲良く、賃貸経営の安心を確保していきましょう!