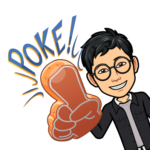こんにちは!
RISO 店長ハチです。
賃貸経営を始めたばかりの新米大家さんにとって、退去後の工事は避けられない課題の一つです。
築20年のマンションを相続した場合、借主が退去するたびにどのように工事を進めるべきか迷うこともあるでしょう。
今回は、退去後の工事を上手に対処するためのポイントをお伝えします。
今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。
- 退去後の工事の目的
- 工事の種類
- 平成以降の賃貸事情
- 工事の必要性を見極めるカギ
1. 退去後の工事の目的
退去後の工事は、単なる修繕ではなく「次の借主に選ばれるための準備」です。
つまり、大家としては「貸室の商品化」を意識することが大切です。
次に住む借主が魅力を感じ、早く決まるような部屋作りを目指します。
2. 工事の種類
工事には大きく分けて以下の2つの種類があります。
1.原状回復工事:
退去前の状態に戻すための工事。
例えば、畳の交換や壁クロスの張替えなどがこれに該当します。
2.価値を上げる工事:
部屋の魅力を高めるための工事。
これには、最新設備の導入や内装のグレードアップなどが含まれます。
3.工事を行わない場合もあります。
地域の最低ラインの賃料で募集するのであれば、畳や壁クロスが多少傷んでいても、大家としてはクリーニングのみで次の入居者を迎えることを選択することも可能です。
3. 平成以降の賃貸事情
近年、一定以上の入居期間を経た場合、畳や壁クロスを新しくするのが一般的になっています。
新しくないと次の募集に影響が出ると考える大家が多いためです。
この点を踏まえ、退去後の部屋を整える際には、時代に合わせた修繕やリフォームが必要になるかもしれません。
4. 工事の必要性を見極めるカギ
工事は「行うべきかどうか」を冷静に判断することが重要です。
必ずしもすべての工事を行う必要はなく、賃貸物件としての商品価値を考慮して、必要な工事だけを行うことが賢明です。
修繕に重点を置きすぎず、次の入居者がどの程度のリフォームを求めているかを見極めることが成功のカギとなります。
退去後の工事は、次の借主を迎えるための「商品化」の一環です。
すべての修繕や工事を行うのではなく、地域の賃料相場や物件の特性に応じた適切な対策を取ることが重要です。
次の入居者に魅力的に映る物件作りを心がけつつ、工事の必要性を冷静に判断していきましょう。
このように、工事の目的や範囲を適切に見極め、無駄なく効果的な対処を心がけることが、賃貸経営の成功につながります。
X(旧Twitter)を始めましたのでフォローしてくれたら嬉しいです。