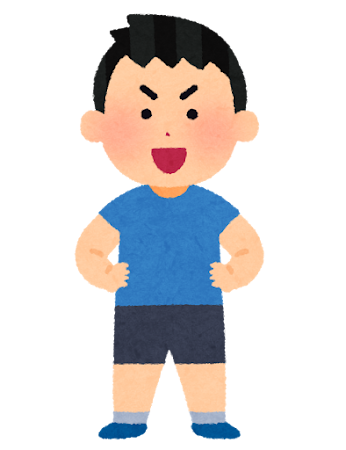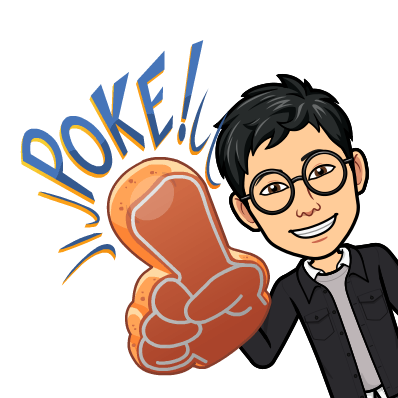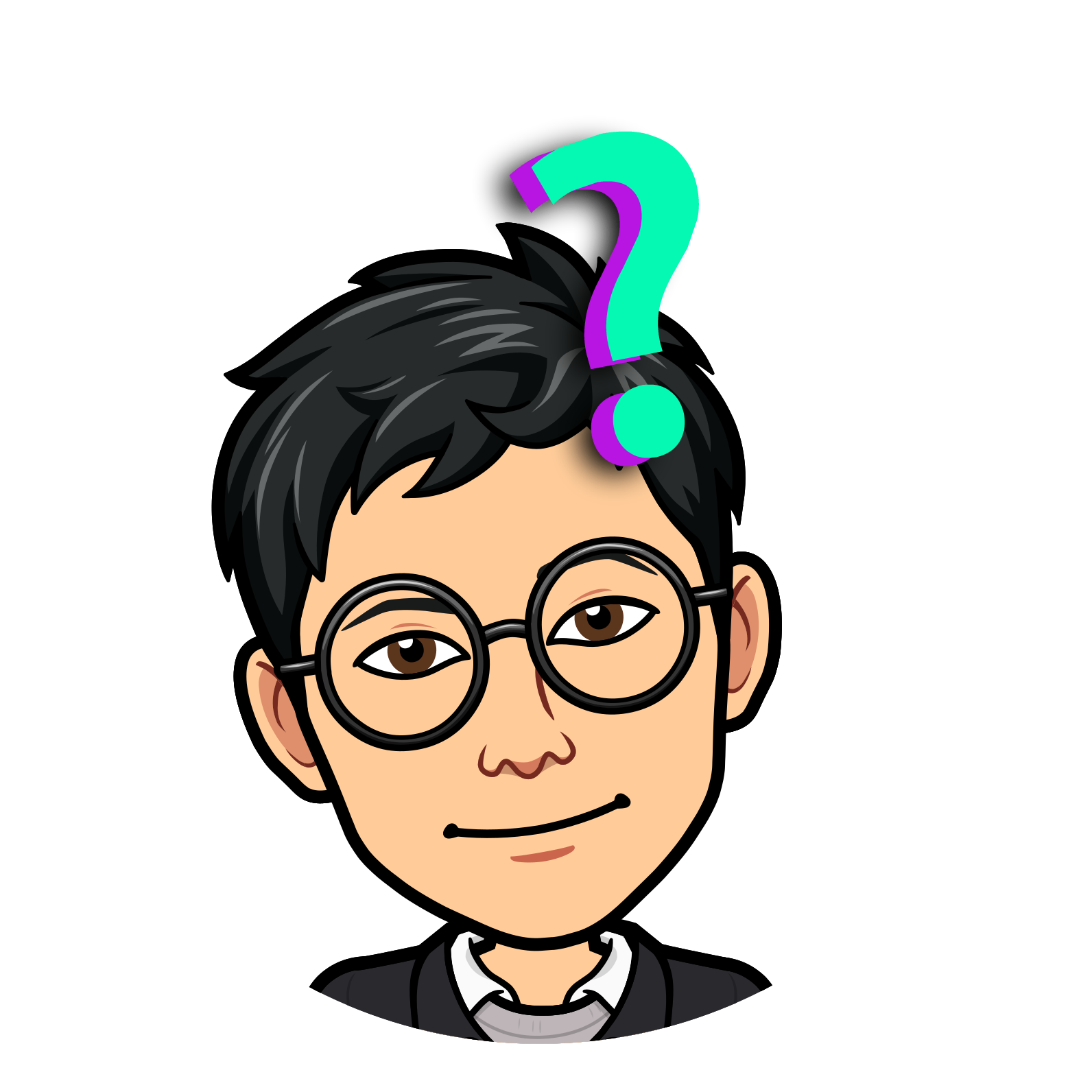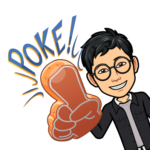ある日、タレントの岡田准一さんが演じる営業マンが登場するテレビCMを見て…
「これはいい!」と思いましたが、
これって安易でしょうか?
ご意見とアドバイスをお願いします。
ただし、よく考えずに飛びつくと、気づいたら賞味期限切れの選択肢を選んでしまう可能性があります。
さあ、新米大家さん、一緒に土地活用の「お惣菜」を吟味していきましょう!
と言うことで…
こんにちは!
RISO 店長ハチです。
今回は、土地活用の基本についてご紹介していきたいと思います。
今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。
- 土地活用の基本的な考え方
- 資金調達の選択肢と影響
- 土地活用の種類と企画の重要性
- 複数案を比較検討する大切さ
- 土地活用トレンドとリスク要因
1. 土地活用の基本的な考え方
資金の工面方法で事業の味付けが決まる
CMで「土地の半分を売却」と言っていましたが、ここで注目するのは「何を売るか」ではなく「何を残すか」です。
土地の売却は、たしかに簡単な資金調達方法です。
ただし、金融機関から借入れたり、等価交換で建ててもらったりする手段も検討可能です。
2024年現在、AIによる融資審査も増えていますが、「土地活用AI」のようにあなたの願い通りの未来を保証してくれるわけではありません。
例えるなら、「ご飯に何をかけるか」問題です。
売却してすっきりした白ご飯を選ぶか、借入してしっかり具だくさんのおかずを楽しむか。
どちらも味がありますが、自分の「胃袋」に合った選択をすることが重要です。
2. 資金調達の選択肢と影響
土地活用は企画が命、焦らず吟味を
次に重要なのは「何を建てるか」です。
2023年の岡田准一さんはテナントビルを推奨していましたが、2024年の今、AIやリモートワークの普及で
…という声も聞こえてきます。
例えば、駐車場を改良してEVスタンド付きにする、または、戸建て賃貸住宅を建てるといった「現代の風」を捉えたアイデアも考えられます。
ちなみに、マンションかテナントかを選ぶのは、まるで「ラーメンかそばか」選ぶようなもの。
どちらもおいしいですが、食べたいものは日によって違います。
土地の周辺状況やトレンドを調査し、
…と土地に問いかけてみてください(笑)。
3. 土地活用の種類と企画の重要性
提案する会社の得意技を見極める
岡田准一さんのCMが2024年にも健在かはさておき、営業マンが
…と言う理由を探ることも大事です。
その会社が仲介業を得意としているのなら、「売却」が得意な分野だからその提案をしている可能性があります。
まるでラーメン屋さんで「そばを出せ!」と注文するようなものです。
それぞれの専門店には得意分野があります。
つまり、土地活用の相談相手も「餅は餅屋、ビルは建築屋」に相談するのが一番。
いろいろ試食して、自分に合う味を探しましょう。
4. 複数案を比較検討する大切さ
複数の案でシミュレーションする
最後に、土地活用のシミュレーションをしてみます。
2024年11月現在の見通しとして、キャッシュフローや借入額、リスクなどを慎重に考えることが肝要です。
たとえば以下のようなシナリオを考えてみましょう。
A案:土地の半分を売却してテナントビルを建設
- 土地売却価格: 1億5000万円
- 建築費: 1億5000万円(鉄骨造マンション150坪)
- 実質利回り: 5%
- 年間キャッシュフロー: 1500万円
B案:土地を売却せず、借入で建設
- 借入額: 3億円(金利2%、30年返済)
- 年間キャッシュフロー: 1670万円(年間返済額1330万円を差し引き)
A案は「無借金」ですが土地の価値を半分失うリスクがあり、
B案は「借金3億円」というプレッシャーが…。
つまり、どちらを選ぶかは「あなたが夜ぐっすり眠れる方法」を選ぶのがベストです。
5. 土地活用トレンドとリスク要因
結論
土地活用は「焦らず、慌てず、じっくりと」。
何かを始めるとき、「失敗しても笑えるか?」と自分に問いかけてみてください。
そして、選択肢をシミュレーションすることで、土地活用の未来が見えてきます。
土地に笑顔を、そしてあなたにも笑顔を!
土地活用を成功させるためには、「資金の調達方法」と「具体的な企画」を軸に、リスク許容度や時代のニーズに合った選択を行うことが重要です。
また、提案する会社の意図を見抜き、複数案を比較検討することで、キャッシュフローやリスクを具体的に把握する習慣が身につきます。
今回の記事では、現代特有のトレンドやリスクを踏まえつつ、初心者でも楽しく理解を深められるように、なるべく噛み砕き分かりやすい解説を心掛けてみました。
土地活用は人生の大事業!
焦らずじっくり、自分に合った答えを見つけて、未来に笑顔を咲かせましょう。