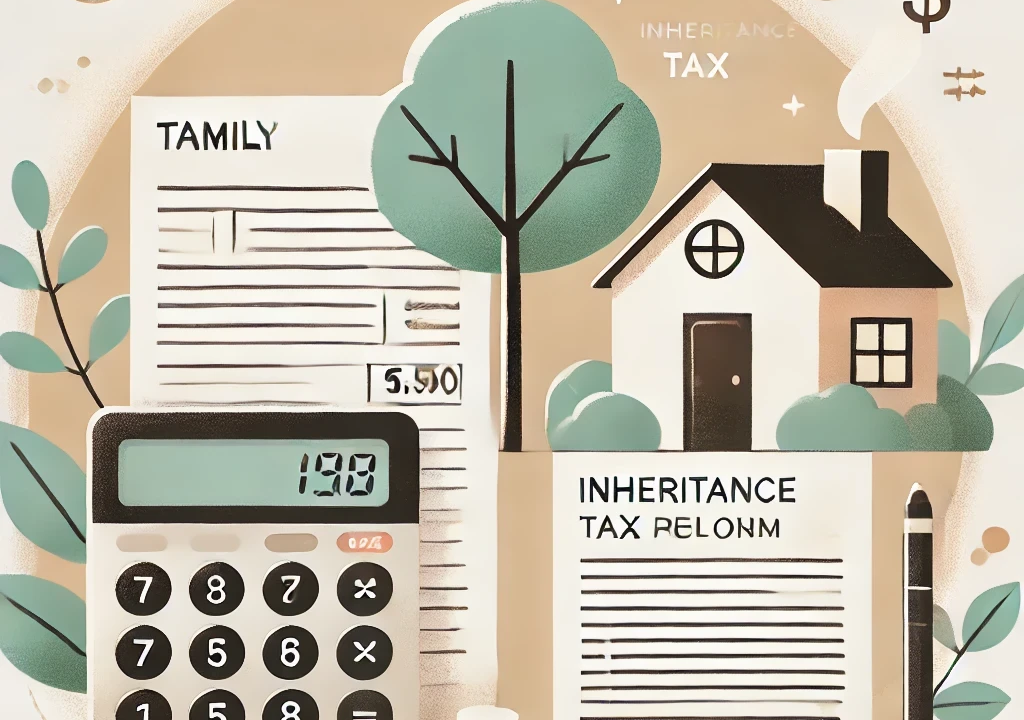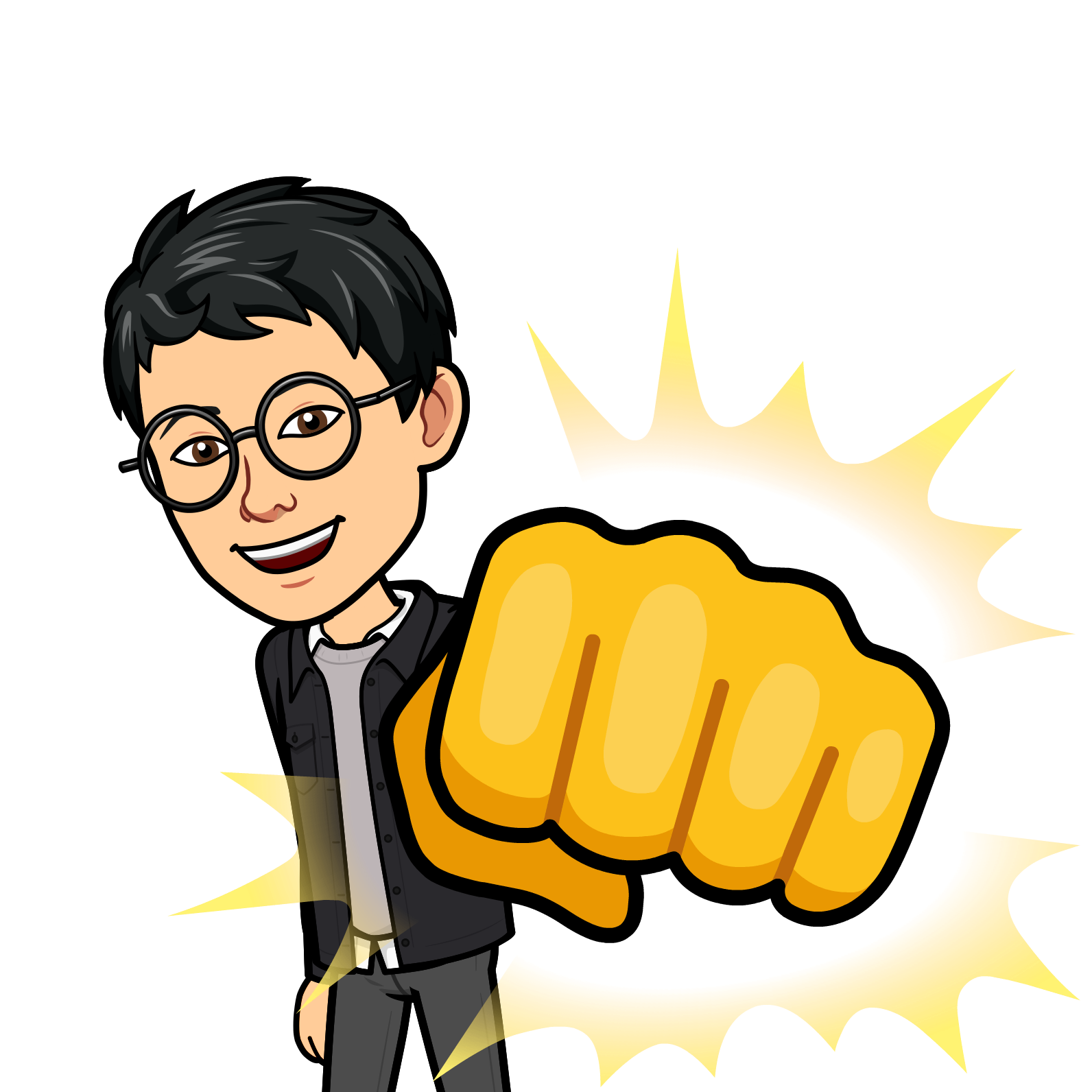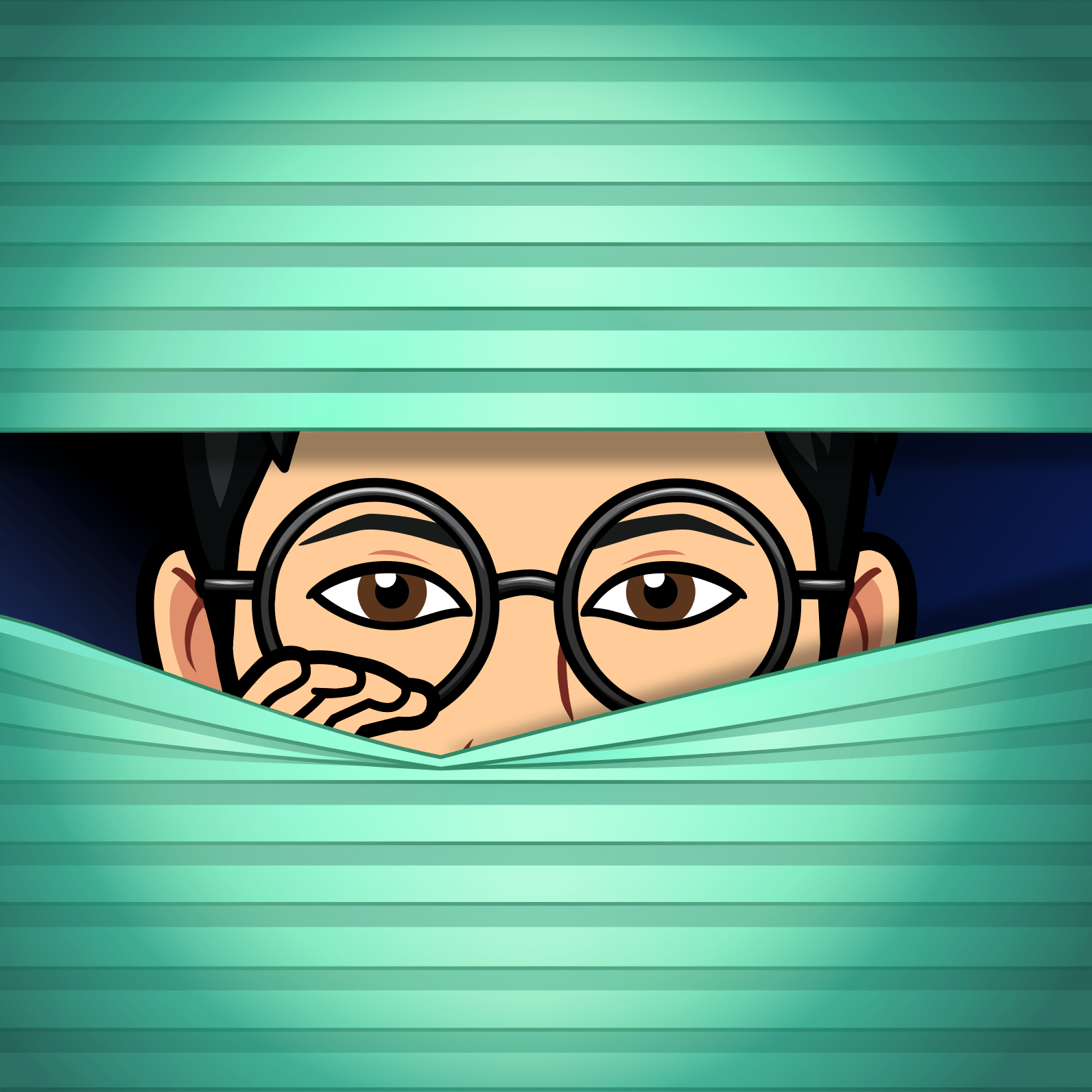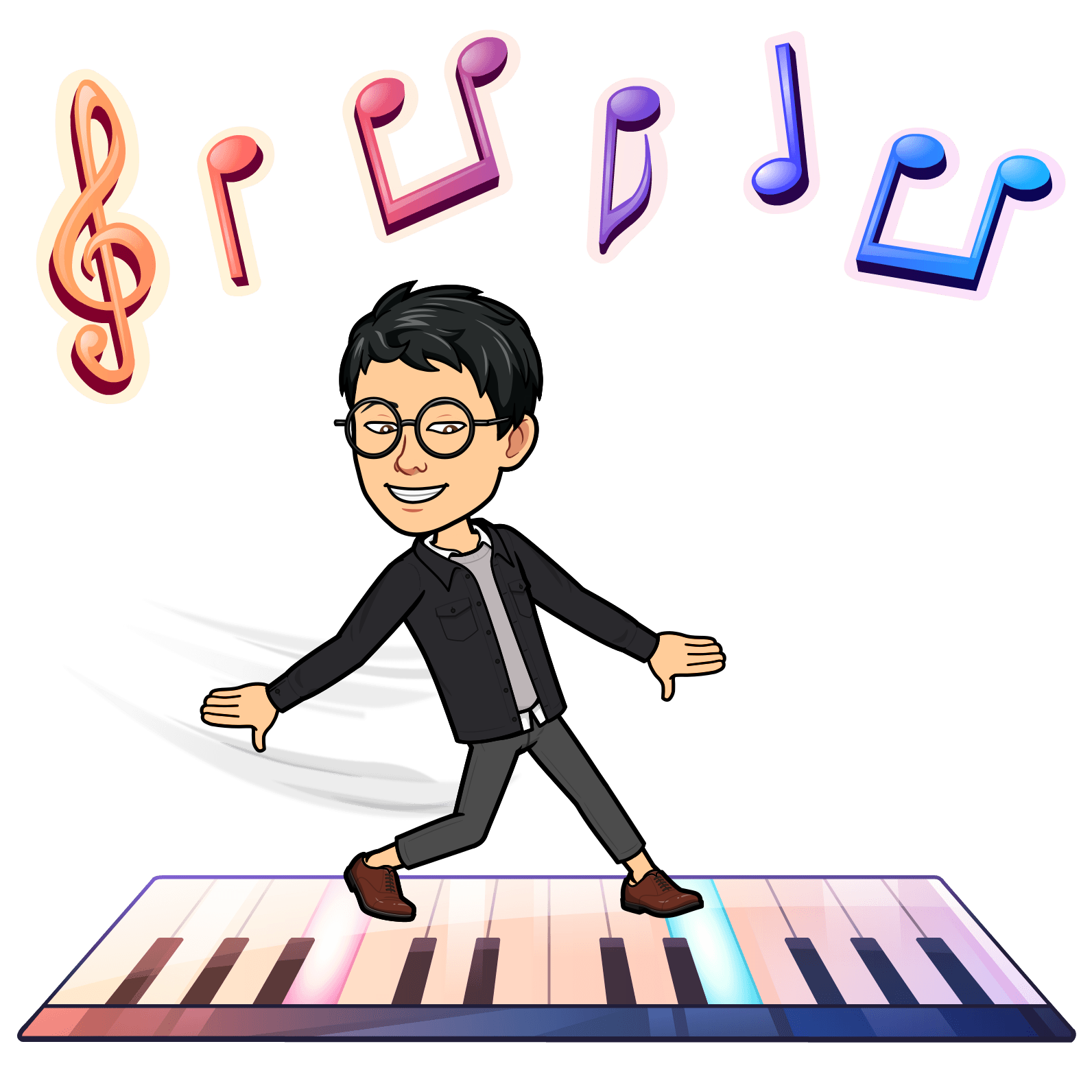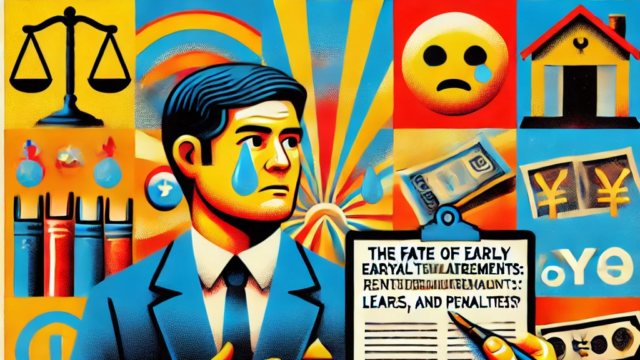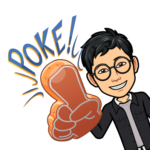いきなりですが、宅建試験問題です。
2024年(令和6年)の税制改正により、相続税・贈与税について次の事項が定められました。以下のうち正しいものはどれか。
- 相続時精算課税制度では、2024年から毎年110万円までの贈与については無税で贈与でき、贈与財産は将来の相続財産に加算されないため、節税対策として有利である。
- 暦年贈与制度の加算期間が3年から7年に延長され、相続が発生する前の7年間の贈与財産は全て相続財産に加算されることが定められている。
- 相続時精算課税制度の基礎控除額は累計2,500万円で、これを超える贈与には一律20%の贈与税がかかるが、110万円を超える場合には別途申告が必要である。
- 暦年贈与における相続財産への加算対象期間が延長されたが、4年目以降の贈与財産の合計額から100万円を控除した残額のみが加算されるため、控除対象外となる金額はすべて非課税扱いとなる。
【解答選択肢】
- 正しいのは 1 と 2 のみ
- 正しいのは 1 と 3 のみ
- 正しいのは 3 のみ
- 正しいのは 1 と 4 のみ
解答:2. 正しいのは 1 と 3 のみ
解説
2024年の改正により、相続時精算課税制度では毎年110万円までの贈与が無税で行えるようになり、この贈与分は将来の相続財産には加算されません。
したがって、節税効果を狙える制度として改正が施されました。
選択肢2:誤り
暦年贈与の加算期間は3年から7年に延長されましたが、7年間の全ての贈与が加算対象になるわけではありません。
4年目以降の贈与財産の合計額から100万円を控除した金額のみが相続財産に加算されます。
相続時精算課税制度では、累計2,500万円までは基礎控除として贈与税がかからない仕組みです。
しかし、110万円の無税枠を超えた場合は申告が必要となり、累計2,500万円を超える部分には一律20%の贈与税が課されます。
選択肢4:誤り
4年目以降の贈与財産の合計額から100万円を控除した残額が加算されますが、「控除対象外の金額がすべて非課税扱い」とはなりません。
控除されない部分の金額は贈与税の課税対象となります。
こんにちは!
RISO 店長のハチです。
2024年もラストスパート、今年も税制改正がガンガン来ていますよ!
年末の風物詩と化した税制改正、もはや
…と意気込んでいる方も多いんじゃないでしょうか?
さて、今回の主役は相続税・贈与税の改正ポイント。
これからの財産の管理・贈与プランをしっかり見直していきましょう。
今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。
- 相続時精算課税制度の改正内容
- 暦年贈与の加算期間延長
- 制度の選択方法と今後の見通し
1. 相続時精算課税制度の改正内容
この「相続時精算課税制度」、かつては「精算課税…?」と怪訝な顔をされがちな制度でしたが、今年の改正で少しばかり脚光を浴びることになりました!
この制度は60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子や孫に贈与をする場合に、累計で2,500万円までは無税で贈与できるというものです。
…が、
まさに「大盤振る舞い…の後に冷や汗」という感じですね。
2024年1月からは、なんと毎年110万円までの贈与が無税でできる特典が追加されました!
これ、税制界の「サブスク」みたいなもんです。
毎年ちょっとずつ贈与することで、「将来の相続財産に加算されない」という特典付き。
小出しの贈与で節税の道が開けるかも?!
さらに、不動産を贈与した場合に災害が発生したらその分を控除できるという制度も。
つまり、家を贈与しても「え、まだ加算されるの?」という心配が減るわけです。
2. 暦年贈与の加算期間延長
さて、もう一つの選択肢、暦年贈与。
こちらも改正がありました。
「相続が始まる前の3年以内に贈与した財産が相続財産に加算される」というルールが、「3年が7年に延びる」という、ちょっと涙目な増税です。
3年が7年って、受験勉強なら気が遠くなるレベルですが、今回はそうはいきません。
とはいえ、7年分全てが対象になるわけではなく、4年目以降の贈与額から100万円を控除した分だけが対象になる仕組み。
もう「税制の計算、まるでパズル!」ですね。
2024年1月1日以降の贈与にはこの新ルールが適用されます。
さて、この暦年贈与と精算課税、どちらを選ぶべきか?
これは、贈与のペースや資産の額によって大きく変わります。
例えば「毎年ちまちま110万円贈与するのが面倒」という方には、暦年贈与の方が有利かもしれません。
3. 制度の選択方法と今後の見通し
どちらの制度も一長一短があります。
精算課税は年間110万円の非課税枠があるものの、贈与財産が大きいと相続時に加算される金額も膨らみます。
一方、暦年贈与は加算期間が長くなるものの、贈与額が大きくなるほど節税効果が見込める場合も。
最終的には、「どれだけ資産をこまめに贈与するか」という“贈与愛”が鍵を握ります。
小分けに贈与していくのか、それとも一気に贈与して相続税と向き合うのか…
皆さんのお財布の中身と相談ですね。
そして2025年以降もさらなる改正が見込まれています。
…ということで、最新情報には要注意。
次の改正で「税制ロイヤルパス」みたいな制度が登場することを願いつつ、今年の年末も税制パズルを楽しんでいきましょう!
この記事では、2024年の税制改正により、相続時精算課税制度で毎年110万円までの無税贈与が可能になり、不動産贈与では災害による控除が追加されるなど、節税効果が狙いやすくなった点を解説しました。
また、暦年贈与の加算期間が3年から7年に延びたため、贈与のタイミングや金額に注意が必要なこともわかります。
どちらの制度が有利かは、贈与する資産や相続までの期間に応じて異なるため、計画的な判断が求められます。
税制改正は複雑ですが、制度の理解を深め、今後の財産管理を前向きに考えられる一助となれば幸いです。
税制改正は年末の風物詩!
次の年も心穏やかに迎えるために、今からしっかり準備を!