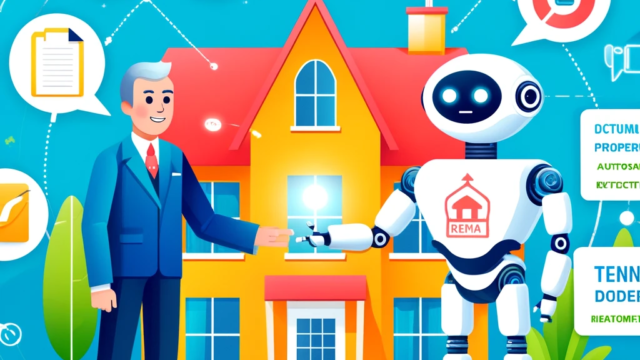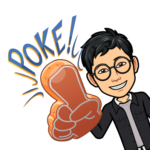こんにちは!
RISO 店長ハチです。
今回は公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)が会員企業に行った調査から日管協短観をご紹介します。

発表した第27回賃貸住宅市場景況感調査(調査対象期間 :2022年4月~2023年3月)は、データとしては2年前と少し古く、最新のデータが気になるところですが…
当協会が発表した最新の調査結果となっております。
この中から興味深いデータや傾向をご紹介します。
(この調査では全国を、「首都圏」「関西圏」「その他のエリア」と3つに分けています)
この調査は、賃貸業界の動向を把握し、賃貸管理企業が適切な戦略を立てられるように情報を提供することを目的としています。
今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。
- 賃貸市場の成約件数・賃料の動向
- 管理報酬と借上料率の首都圏と他エリアの比較
- 入居率は高く滞納率は低い理由
- 平均居住期間長期化傾向とトラブルの減少
1. 賃貸市場の成約件数・賃料の動向
調査結果によると、成約件数は全国的に増加しており、特に関西圏で顕著な増加が見られました。

一方、成約賃料については、「変化なし」が全国で4割以上を占めるものの、首都圏で全体の「増加」比率が5割以上を占めたのに対し、関西では「変化なし」が6割弱。

DI値推移は全てにおいて、前年度よりも上昇。特に、マイナスに疲れていた1R~1DKが大きく上昇し、プラスに振れました。
成約賃料の上昇要因としては、新築をを中心とした建築関連物価上昇の影響により賃貸市場における利回りが低下したこと、テレワークの普及といった業務形態の変化により賃料が多少上がってもより広いスペースやより充実した設備を求める層が増えてきたことなどが主な要因と思われます。
2.管理報酬と借上料率の首都圏と他エリアの比較

管理報酬については、全国で「5%」が最も多く、関西圏では「3%」と「5%」の二分化が見られます。

借上料率については、首都圏で「90%~94%」の割合が高く、他エリアではインフレの影響で借上料率が低下しています。
首都圏以外では人件費高騰などのインフレ要因によりサブリース会社の経営コストが上昇したことで借上げ料率は下方シフトしたのに対し、首都圏では家賃の上昇に加え礼金や更新料などの増収要因がインフレ要因を上回り、借上げ料率は逆に上方シフトしたと考えられます。
3.入居率は高く滞納率は低い理由
全国の入居率は委託管理物件で94.0%、サブリース物件で97.3%と高い水準にあります。
首都・関西圏においてはサブリースを中心に新築物件仕入れ戸数を増やし、平均居住期間についてはコロナ緩和の影響もあり対前年度マイナスとなったのに対し、その他のエリアでは既存物件を中心に仕入れ戸数を増やし、平均居住期間については他エリアとは逆に対前年度プラスとなったことが要因と思われます。

滞納率についても、全国的に低く抑えられており、特に2か月以上の滞納率は0.3%と安定しています。
全国的に2か月滞納が昨年度同様低率に留まっているのは、滞納保証会社による代位弁済が浸透している影響大と思われます。
関西圏の滞納率が他のエリアに比べ高いことについてはさらなる分析の必要性を感じております。
4. 平均居住期間長期化傾向とトラブルの減少

平均居住期間は全国で単身者が約3年、ファミリーが約5年と長期化傾向が続いています。
平均居住期間についてはどのタイプでも前年度と大きな違いはなく、関西圏において単身タイプの平均居住期間が短いことは、関西圏の滞納事が高いこととの相関があるのか検討を要するところであります。

また、入居時や退去時のトラブルに関しては、全体として減少傾向にあり、賃貸管理の改善が伺えます。
全体として退去後トラブルは減少したが、特に関西部における減少は各項目とも顕著であります。
2021年6月施行の賃貸住宅管理業法により管理会社の意識が高まったことに加え、大阪版原状回復ガイドラインの策定等、各自治体の独自の取り組みなども貸主及び管理会社の意識向上に寄与している可能性があります。
この調査結果は、賃貸管理企業やオーナーが市場の動向を把握し、戦略を見直すための有益なデータを提供しております。
この記事で紹介しているデータは、2022年度(2022年4月~2023年3月)に基づくもので、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)が発表した最新の調査結果です。
現在は2024年ですが、この記事の時点で2022年版以降の更新はまだ行われていません。
そのため、最新の賃貸市場の状況やトレンドがどのように変化しているかが気になるところです。
日管協の次回調査に期待しつつ、今後も市場の変動に注目しながら賃貸経営に役立てていきましょう。