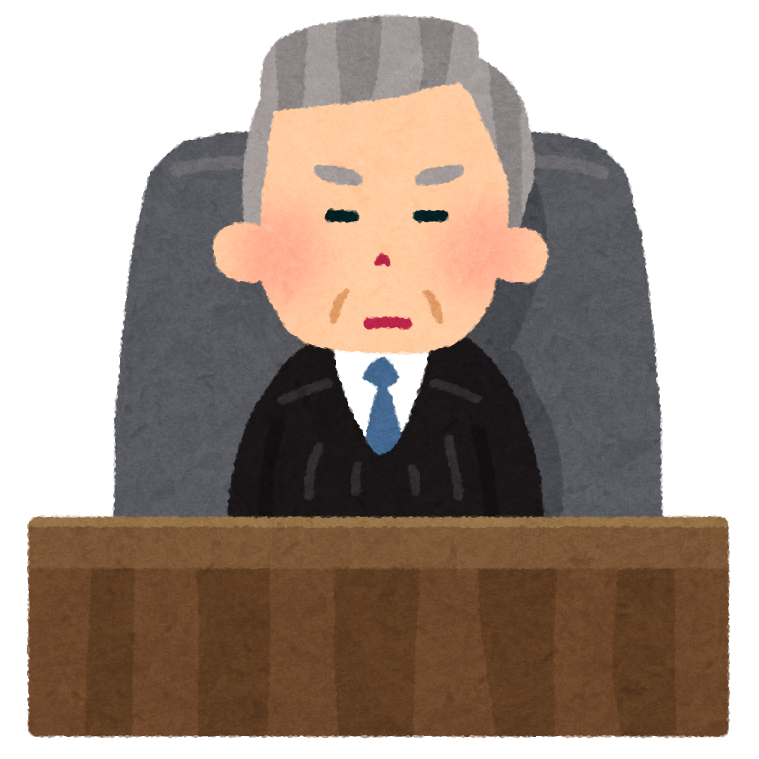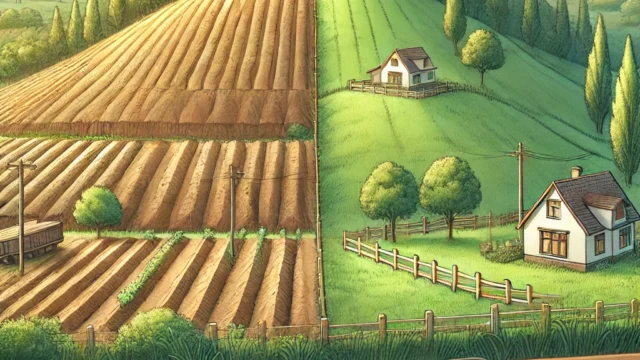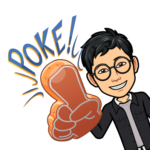先ずは今回の記事に関連して、宅建士試験対策の問題です。
今回の内容をもとに本試験レベルの問題を作成しました。
解答と解説もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
賃貸借契約の中途解約制限条項および違約金に関する以下の記述のうち、最も正しいものはどれか。
- 借主が契約期間中に一方的に解約した場合、契約に定められた違約金として、貸主が次の賃借人を確保するまでに必要とされる期間全体の賃料相当額が請求される。
- 裁判例において、違約金として請求できる金額は、貸主が新たな賃借人を確保するために必要な期間(概ね6ヵ月~1年分)の賃料相当額を上限とするのが妥当とされる。
- 民法の規定により、賃貸借契約において解約権が留保されていない場合でも、借主は裁判所の判断により中途解約が認められ、違約金の支払いは免除される。
- 違約金の額は契約自由の原則に基づき、双方の合意があれば無制限に高額に設定できるため、裁判所の判断は介在しない。
正解:2
解説
本問題は、賃貸借契約における中途解約制限条項の法的背景と、裁判例(例:東京地裁平成8年8月22日判決)に基づく違約金の適正な設定について問われています。
裁判例では、貸主が次の賃借人を確保するために実際に必要な期間を考慮し、概ね6ヵ月から1年分の賃料相当額を違約金の上限と認める判断が示されています。
したがって、選択肢2が正しい記述となります。
前回の記事を見てた方なら楽勝問題でしたね!
こんにちは!
RISO 店長ハチです。
賃貸経営のプロとして、今日も法律のネタ帳を片手に、皆さんのためになる情報をお届けします。
今回のテーマは、前回の続き「賃貸借契約の中途解約を制限する条項は有効か(後編)」、つまり「契約期間中、勝手に退去できちゃうのか?!」という重い話ですが、その真相に迫っていきましょう!
今回の記事を読むことで、以下のポイントが理解できるようになります。
- 中途解約制限条項の意義
- 契約書上の「解約権留保」の重要性
- ユーモラスなアプローチによる理解の促進
- 真剣な賃貸経営の心得
1. 中途解約制限条項の意義
借主の中途解約禁止ってホントにあり得るの?
まず、民法617条と618条をざっくり要約すると、
賃貸借契約で期間が定められている場合でも、貸主や借主のどちらかに期間中に解約できる権利があるなら、その解約の申入れの日から所定の期間を経過して契約が終了する
…と定めています。
つまり、もし契約書に「解約できる権利」があらかじめ与えられていなければ、借主は途中で「もういいや!」と退去することは認められないわけです。
法律の世界では、これが「解約権留保の有無」で決まる、といった具合に厳格に判断されています。
まるで漫才コンビで「解約権ボケ」が決まっていないと、一方的なツッコミ(=退去)が通らない、という感じでしょうか。
2. 契約書上の「解約権留保」の重要性
最高裁と東京地裁が示した、借主退去の鉄則
まず、土地の賃貸借契約においては、最高裁判所昭和48年10月12日判決が登場。
この判決では、
賃貸借の期間の定めは、もし一方だけが解約権を留保している場合、その留保した側の利益のために設けられたものだが、そうでなければ、貸主も借主も双方の利益のためのもの
…と解され、解約権が留保されていない場合、借主が期間内に一方的に解約申入れをしても無効とされる、と判断されました。
要するに、
…という法律のメッセージが込められているわけです。
建物の賃貸借契約に関しては、最高裁の明確な判断はないものの、東京地方裁判所平成23年5月24日判決が参考になります。
このケースでは、契約期間が20年にも及ぶ長丁場の契約で、借主は残り約1年4ヵ月あるにもかかわらず退去を試みました。
しかし、契約上「解約禁止」の特約がある以上、たとえ建物をほとんど使っていなかったとしても、残りの期間分の賃料を支払う義務は免れませんでした。
店長ハチ(もちろん、もし貸主が次の入居者をすぐに見つけたり、管理費用の一部が節約できた場合は、その分だけ調整されるんですけどね。)
3. ユーモラスなアプローチによる理解の促進
短期契約の場合はどうなる?~笑い話にもなる解約事情~
ここでひとつ、笑い話にもなりかねないケース。
20年という長大な契約なら「中途解約禁止」で鉄則ですが、もし賃貸借契約が2~3年と短期の場合、残存期間が半年から1年を超えると、
…と、公序良俗に反すると判断される可能性があるのです。
その結果、借主は契約に縛られず、たとえば違約金として「6ヵ月分の家賃」で途中解約が認められるかもしれません。
まるで、インターネットの契約と同じで「そろそろ解約したいっす!」と言ったら、違約金を払えばOKって、笑いあり涙ありのレンタル事情ですよね。
なお、居住用賃貸借契約の場合、借主のほとんどが個人(非事業者)ですから、消費者契約法の適用対象となります。
消費者契約法の視点からの留意点については、次回改めて詳しく解説する予定ですので、そちらもお楽しみに!
4.真剣な賃貸経営の心得
結局のところ、賃貸借契約において借主の中途解約を禁止する条項は、契約の趣旨や双方の利益を踏まえて設けられているものであり、法律もそれを支持しています。
しかし、契約期間の長短や実際の事情によって、適用の仕方や違約金の金額は変動する可能性があります。
まるで、ブログのネタも長さや閲覧者の反応で変わるように、賃貸契約も柔軟な対応が求められるのです!
賃貸経営の現場では、契約書の一文一文が、面白いネタにもなるほどのドラマを秘めています。
借主も貸主も、しっかりと契約内容を把握し、場合によっては柔軟な解約交渉を行うことが求められます。
賃貸経営のプロとして、私が伝えたいのは「契約書の中身は笑い話にできないほど大切」だということです。
結局、賃貸借契約の中途解約制限条項は、貸主のリスク補償と借主の権利保護とのバランスを保つための重要な仕組みであり、法と実務の両面から柔軟な対応が求められると言えるでしょう。
皆さんも、契約前にしっかり確認して、後悔のない賃貸ライフを送ってくださいね!
次回は、消費者契約法の視点から見た賃貸借契約の留意点について、さらに掘り下げたお話をお届けします。
どうぞご期待ください!